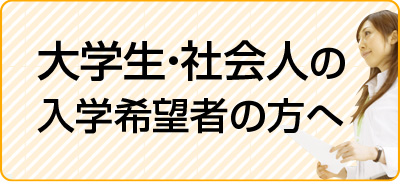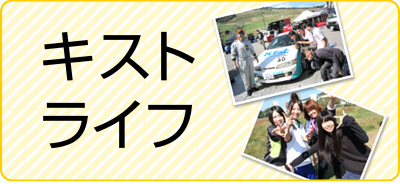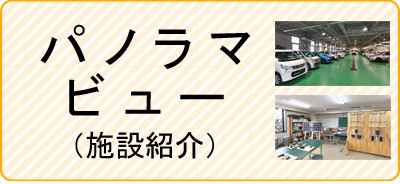これがKistの実践的授業
これがKistの実践的授業
自動車工学科には、2年で2級整備士を目指す2級コースと、4年で1級整備士を目指す1級コースを設置。エンジン・電気系統・足回りなど、自動車の基本メカニズムを学び、応用を積み重ねながら確かな知識や技術が身につくよう、実習と学科の両面で指導しています。
自動車整備士への最短コース。 Kistなら実技試験が免除!

自動車整備士を目指すなら、まず欠かせないのが国家資格である2級自動車整備士(ガソリン・ディーゼル)。通常は5年以上かかるところ、Kist 2級コースなら卒業と同時に2級整備士の受験資格が取得でき、加えて実技試験が免除されます。効率良く資格が取得できるため、検査員などの資格を取って、よりレベルの高い整備士を目指すことも可能です。
また、Kist 1級コースなら卒業と同時に1級整備士の受験資格が取得でき、加えて実技試験が免除されます。
各メーカーの様々な車種を取り揃えています。
各メーカーによって、自動車のつくりや部品名にも違いがあります。Kistではトヨタ、ニッサン、ホンダ、スズキ、マツダ、スバル、ダイハツ、スズキ、三菱、日野、いすゞなど、様々な車種が用意されています。実習では普通車をはじめ、ハイブリッド車、電気自動車、軽自動車、トラックなど、いろんなタイプの車を取り扱っています。
実習時間が充実。 だから、技術力で差がつくのです。

業界で通用する本物の技術を育成する、それがKistのカリキュラムの特徴です。なぜなら、実習時間はどこよりも豊富なのです。とにかくクルマに触って体で覚える。だから、Kistの卒業生は優秀な技術者として活躍できるのです。
ハイブリッドカーやコンピュータ診断など、最新技術も学習。
ディーラー整備士による特別講習会を定期的に行っています。最新車種を導入し、コンピュータ・タブレットを使った故障診断の直接指導が受けられます。また、エンジンとモーターを組み合わせて走行するハイブリッドカー(HV)や、電気自動車(EV)といった、業界の動向に合わせた新技術についても学習します。
【選択授業】応用技術や知識を深く追究しよう。
- コーティング
- モニターオーディオ取付
- カスタム技法
自動車工学科では、コーティング、モニターオーディオ取付、カスタム技法といった特別授業を実施しています。自動車に関することを幅広く学び、一流の整備士を目指そう!
カリキュラム

【シャシ実習】
トランスミッションや走行装置などの構造を理解します。アライメントテスターを使った実習では、タイヤの角度・取付状態を数値で確認し、点検や調整を行います。

【エンジン実習】
エンジンの仕組みと、その測定・分解・組み付けの技術を学びます。たくさんの実習車に触れ、繰り返し作業を行うことで、実践的な技術を身につけます。

【電装実習】
ヘッドライトやワイパーなどの電気装置部品の構造や、電気配線の見方、点検の仕方を学習します。

【新技術・公害対策】
ハイブリッドカーや電気自動車も実習車として導入。時代の流れに沿って、最新の技術も学んでいきます。
■2級コース
| 1年次 | 2年次 |
||
|
●エンジン実習Ⅰ ●シャシ実習Ⅰ ●電装実習Ⅰ ●工作実習Ⅰ ●測定実習 ●総合実習Ⅰ ●自動車工学 ●電気・電子理論 ●整備測定機器 ●エンジン構造Ⅰ ●エンジン整備Ⅰ ●シャシ構造Ⅰ ●シャシ整備Ⅰ ●電装品構造Ⅰ ●電装品整備Ⅰ ●二輪自動車Ⅰ ●材料 ●燃料・潤滑剤 |
●エンジン実習Ⅱ ●シャシ実習Ⅱ ●電装品実習Ⅱ ●総合実習Ⅱ ●自動車検査作業Ⅱ ●図面 ●新技術・公害対策 ●検査機器 ●法規Ⅱ ●エンジン構造Ⅱ ●エンジン整備Ⅱ ●シャシ構造Ⅱ ●シャシ整備Ⅱ ●電装品構造Ⅱ ●電装品整備Ⅱ ●自動車検査 ●故障原因探究 ●力学・数学 |
■1級コース
| 1年次 | |||
|
整備の基本をしっかり学ぶ
学科と実習を通じて、基本的な整備技術の習得を目指します。通常授業以外にも、ディーラー整備士による車両点検や診断機の操作方法など学ぶ特別授業も実施します。
|
●エンジン実習Ⅰ ●シャシ実習Ⅰ ●電装実習Ⅰ ●工作実習Ⅰ ●測定実習 ●総合実習Ⅰ ●自動車工学 ●電気・電子理論 ●整備測定機器 ●エンジン構造Ⅰ ●エンジン整備Ⅰ ●シャシ構造Ⅰ ●シャシ整備Ⅰ ●電装品構造Ⅰ ●電装品整備Ⅰ ●二輪自動車Ⅰ ●材料 ●燃料・潤滑剤 |
||
| 2年次 | |||
|
実践的な整備技術を習得
2年次からは実車を使った点検整備や故障探求、検査ラインでの検査業務といった、現場を意識した実践的な実習も行います。2年次修了時には、2級自動車整備士資格(ガソリン・ジーゼル)の取得を目指します。
|
●エンジン実習Ⅱ ●シャシ実習Ⅱ ●電装品実習Ⅱ ●総合実習Ⅱ ●自動車検査作業Ⅱ ●図面 ●新技術・公害対策 ●検査機器 ●法規Ⅱ ●エンジン構造Ⅱ ●エンジン整備Ⅱ ●シャシ構造Ⅱ ●シャシ整備Ⅱ ●電装品構造Ⅱ ●電装品整備Ⅱ ●自動車検査 ●故障原因探究 ●力学・数学 |
||
| 3年次 | |||
|
整備の先進技術を習得
電気自動車やハイブリッドカーの整備はもちろん、二輪整備も取り入れ、あらゆる自動車の先進技術習得を目指します。担当教員は1級自動車整備士の資格取得者、頼れる存在です。3年次の後半からは、就職活動もスタートします。
|
●エンジン実習Ⅲ ●シャシ実習Ⅲ ●電装実習Ⅲ ●工作実習Ⅲ ●応用計測実習 ●自動車検査作業Ⅲ ●故障探求実習 ●エンジン構造Ⅲ ●エンジン整備Ⅲ ●シャシ構造Ⅲ ●シャシ整備Ⅲ ●2輪4輪整備技術 ●総合診断・環境保全・安全管理 ●自動車材料 ●法規Ⅲ ●法技術Ⅲ ●検査機器、自動車検査 |
||
| 4年次 | |||
|
高度整備技術やビジネススキルも習得
高度な整備技術以外にも、インターンシップを通じて実作業における能力向上を目指します。接客業務や作業説明も未来の整備士には求められます。後期の授業では、1級自動車整備士の筆記と口述の受験対策を行い、難関資格の合格を目指します。
|
●体験実習a ●体験実習b ●体験実習c ●評価実習 点検整備a ●評価実習 点検整備b ●評価実習 故障原因探求 ●評価実習 総合診断 ●サービスマネジメントa ●サービスマネジメントb ●サービスマネジメントc ●自動車概論 |
取得目標資格と就職分野
| 取得目標資格 | 就職分野 |
| ●1級小型自動車整備士※ ●2級ガソリン自動車整備士※ ●2級ジーゼル自動車整備士※ ●中古車自動車査定士 ●乙種危険物取扱者 ●有機溶剤作業主任者 ●ガス溶接技能者 ●損害保険募集人資格 ●電気取扱業務(低圧)資格 ※卒業と同時に実技試験免除 |
●メーカー ●ディーラー(メーカー系) ●大型車ディーラー(バス・トラック) ●輸入車ディーラー(整備・販売) ●整備工場 ●損害保険会社 ●ロードサービス会社(JAFなど) |
学費支援のある企業について
支援条件や金額、支給時期といった具体的な内容は、Kist入学相談室へ直接お問い合わせください。
整備士の魅力紹介動画
整備士の現状ややりがいなど、Kistの卒業生が語っています。
3分程の見やすい動画となっていますので、ぜひご覧ください。